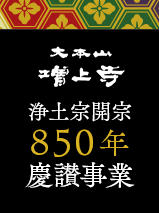浄土宗開宗850年奉賛局だより(11月)
2025.11.01
三解脱門の風景〜言葉と額縁〜
修復中の三解脱門をくぐることができるようになってから、早2か月。正確に言うならば、修復のために三解脱門を覆っている素屋根の一部の通り抜けが可能になって2か月が経ったということです。
また三門楼上にありました十六羅漢像、歴代上人像は慈雲閣に移動、釈迦三尊像は修復のために工房へと運ばれています。
普段私たちは「三門をくぐる」と言います。しかしながら素屋根に覆われた現在は「三門の下を通行」「三門を通り抜ける」と表現したほうがしっくりいく気がいたします。通路を実際に抜けてみますと、幅はそれほどないのですが、結構な長さを感じ、三解脱門を覆っている素屋根の大きさが実感できます。通路は防災防犯上のこともあり、夜間は結界を置き、照明を点灯しています。
通常増上寺の朝の勤行は6時から始まります。夕勤行は午後5時からです。通行可能になった9月はまだまだ暑い時期。いずれの時間も陽光が当たり、メッシュシート上の三門も大殿もキラキラと輝いておりました。11月ともなりますとさすがにいずれの時間も少々暗く感じます。しかしながら、どちらを見ても渋く煌めいて、その存在を示しています。
これまで増上寺をお参りなさる際には三門を通して大殿が臨めました。道路の向かいからでも三門を通して眺めるとその大きさがはっきりとし、そこに至るまでの石段も絶妙な距離感で見えていたと思います。三門修復のためにできた素屋根の通路を抜けることは、実物の三門をくぐる感覚とは確かに違うかもしれません。
通路を境内に向かって進むと、朝には朝日を浴びる大殿が、夕刻には逆光にシルエットとして浮かぶ大殿が鮮やかにあるいは神秘的に目に飛び込んできます。期せずしてできた『額縁効果』かもしれません。
三解脱門がそこにある風景。素屋根がかかった今の風景。自分自身の心と生きている時間が絶妙に綾なし作り出される情景。数年後、修復された三門に歩み近づく時、私たちは「くぐる」という言葉を想起するのか「とおる」という語を用いようとするのか。自身の言葉の表現と共に朱色の額縁効果で映し出される風景がどのようなものかを想像するのが楽しみなこの頃です。
皆様もぜひ訪れて体感下さい。
奉賛局部長 中村瑞貴