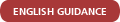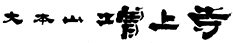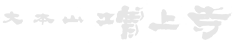徳を積んで
この世から
あの世に逝く人
そこには憂いも恐れも
存在しない
令和7年7月 ブッダ『ダンマパダ』220偈より
「藪入り」という落語をご存じでしょうか。昭和の名人といわれた1人、3代目、三遊亭金馬が演じているのをDVDで見たことがあります。かつての日本には、近世江戸時代から近代明治期以降にかけて「奉公」という働き方がありました。幼いうちから商家などに住み込み、複数年単位で働きます。そうした中、年に2回、1月16日と7月16日に藪入りという休日があり、奉公人は実家に帰ることが許されるのです。落語「藪入り」は、奉公に出た息子が3年振りに親元に帰ってくるというところから始まる人情噺です。藪入りの前夜、どれほど成長したことかを楽しみに待つ両親、つらいこともあっただろうと我が子の苦労を想い、たった1日とはいえ、無事に帰ってきたならば、あれもしてやりたい、これもしてやりたいと、だんだんと話が飛躍していく父親と、それをなだめる母親のやりとりが見どころの一つになっています。
藪入やうれし涙をもらひ泣
松瀬青々
落語に限らず、奉公に出した子どもと親の再会は他人から見ても感動的であったのでしょう。俳句にも詠まれました。
ブッダ(お釈迦様)は「長い間、留守にしていて、遠方から無事に帰ってくる者。親族や友人、親しい人々はその帰還を喜ぶ」(『ダンマパダ』第219偈)と述べています。さらに、徳を積む者があの世に赴くにしても、あたかも親しい人々が喜んで迎えてくれるように、そこには憂いも恐れもないと説いています。あの世に赴く時、お念仏を称えて徳を積むならば、極楽浄土が愛情をもって私たちを迎えてくれる。極楽浄土には再会を喜んでくれる人々がいる。だからこそ憂いも恐れもない。私はそのように思っています。
教務部長 袖山榮輝