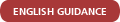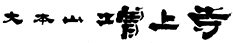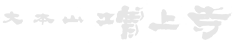お知らせ
お知らせお盆とお施餓鬼
 昔から旧暦の7月15日を中元の佳節とし、年間の無事を祝う習慣があります。日本ではこの中元にお盆とお施餓鬼という行事が結び付いています。各家庭で祖先の霊を祀り、墓参し、僧侶を招いて読経して祖先の功徳を修し、親族の幸福を願う大切な時です。
昔から旧暦の7月15日を中元の佳節とし、年間の無事を祝う習慣があります。日本ではこの中元にお盆とお施餓鬼という行事が結び付いています。各家庭で祖先の霊を祀り、墓参し、僧侶を招いて読経して祖先の功徳を修し、親族の幸福を願う大切な時です。
「お盆」と省略される盂蘭盆の起こりは「盂蘭盆経」に書かれています。それによると、お釈迦様の十大弟子である目連が、修行により神通力を得ました。この喜びを、神通力で亡き両親に伝えようとすると、父は西方浄土に往生しているのに母が見当たらない。母は骨と皮だけの鬼のような姿で、餓鬼道に落ちていたのです。目連はたまらず、母を救う方法をお釈迦様に尋ねました。お釈迦様は、母の苦しみは生前の悪行の報いによるもの、思いやりを忘れ、祖先の供養を怠り、仏・法・僧の三宝を大切にしなかった結果であると答えられました。その後、目連の孝心によって母が救われたと書かれています。
また「お施餓鬼」は、お釈迦様の弟子で、甥でもある阿難のお話です。ある日、阿難の前に鬼が現れ、お前の命はあと3日だと告げて去ります。阿難は、今はまだ人に尽くすことができないでいる修行中の身だから、何とか延命を、とお釈迦様にすがりました。そこで説かれたのが「施餓鬼」です。その年に亡くなった精霊、水子の霊、三界万霊といって広く無縁の霊に施しをする行事です。
故事に共通点のあるこの二つの行事が同じ時期に行われるようになり、正月と並ぶ年間の二大行事になっています。