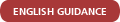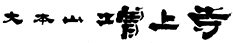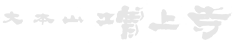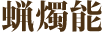 蝋燭能
蝋燭能
増上寺蝋燭能開催のお知らせ
来る12月2日、大殿本堂内にて「増上寺蝋燭能」(主催:大本山増上寺、協力:あすに繋ぐ能の会)を開催することになりました。荘厳な本堂内に蝋燭が揺らめく幽玄のひと時をぜひお楽しみください。
令和5年 増上寺蝋燭能
【日にち】令和5年12月2日(土)
【時 間】16:00 開場
16:30 法要
17:00 開演
【会 場】増上寺大殿本堂
【演 目】狂言「仏師」野村又三郎
能「船弁慶(前後之替)」梅若泰志
【入場券】指定S席:10,000円
指定A席:8,000円
指定B席:6,000円
令和5年10月2日(月)正午より発売開始
【申込先】増上寺オンラインストア
増上寺 薪能の歴史
増上寺の薪能は、江戸時代より、現在の東京タワーの辺りにあった能楽堂で行われていました。
度重なる天災や戦災によって、中止を余儀なくされていましたが、昭和49年、増上寺大殿が復興されたのを機に、境内の特設舞台に場所を移して奉納が再開されることとなりました。
重要文化財の三門と、グラント将軍お手植えの松を背景とした篝火の灯りで演じられる能は、皆さまを幽玄の世界へと誘います。 新緑の木々と朱の三門に彩られる境内での特別な一時をお楽しみください。
- 令和元年度の薪能については「第36回 増上寺薪能のご案内」をご覧ください。


初めて能を見る人のために
能楽とは?
能楽は、日本の古典芸能です。600年以上の古い歴史を持つ能は、国の重要無形文化財にも指定され、海外からも高い評価を得ています。
能楽のはじまりは、室町時代にさかのぼります。観阿弥、世阿弥によって大成された能楽は、その後、江戸時代の式楽として、武家社会を中心に栄、その簡潔で集約された演技、演出による独特の舞台芸術は、後世ににながく受け継がれるべき、貴重なものとなりました。
能楽の歴史と増上寺
 能楽(能)は、社寺の祭礼に奉仕するための猿能楽に、民間で発展した田楽を取り入れたことからはじまった舞台芸術です。観阿弥・世阿弥の親子によって、芸術として大成しました。
能楽(能)は、社寺の祭礼に奉仕するための猿能楽に、民間で発展した田楽を取り入れたことからはじまった舞台芸術です。観阿弥・世阿弥の親子によって、芸術として大成しました。
江戸時代、幕府の儀式芸能として興隆を極めた能楽は、維新後、廃絶の危機に瀕します。しかし、公家・貴族の尽力によって再び盛んに演じられるようになりました。岩倉具視らの融資によって、能楽社(のちの能楽会)が組織され、明治14年には、能楽堂(敷地700余坪、建物340余坪)が現在の東京タワーの辺りに建てられたのは、その頃です。
上覧能演場として栄えた能楽堂ですが、第二次世界大戦において、そのほとんどは灰となります。
そこで増上寺は、昭和49年の大殿復興を機に、薪能を開催することとしました。
薪能で重要なのは、漆黒の闇の中で篝火を焚いて演じる舞台設定です。この難しい条件をクリアした増上寺の境内と、舞台が設置される参道は、日本でも有数の舞台となりました。
出演者は、三解脱門(重要文化財)を背景として、大殿に向かって演技を行い、増上寺本尊、阿弥陀如来に奉納します。江戸三大名鐘の一つである、大梵鐘(高さ3メートル余り、重さ15t)が、開演の合図です。
客席からは、舞台全体が浮き彫りになったように見えます。その迫力は、何にも変えることができません。
「都内最高」の舞台である増上寺で、是非、薪能をお楽しみください。
登場人物と、演者の役柄
能楽は、シキ方、ワキ方、囃子方、狂言方が、それぞれの厳しい修行を経た芸を、一つの舞台に結実させた総合芸術です。どの役が弱体となっても、質の高い舞台にはなりません。
初めて見るときには、演者の役割を把握しづらい方もいらっしゃることでしょう。それぞれの役の基本事項について、ご説明します。
シテ方が演じるもの
- シテ:主役
- ツレ:シテの補助的人物 例えば侍女、相手役など
ワキ方が演じるもの
- ワキ:シテの相手役だが、ツレではない。面はつけない。僧、武士、船頭など、必ず人間の役を演じている点が特徴。
囃子方が演じるもの
- 囃子:管楽器の笛に対して、小鼓と大鼓の複雑な間合いで演奏される音楽のこと。能の楽器は四拍子と言い、笛、小鼓、大鼓、太鼓、で演奏される。3種の打楽器の中で、太鼓だけは等間隔のテンポで演奏される点が特徴。打楽器の音色の違い、テンポの相違、かけ声の気合いが能独特の不思議な興奮と陶酔の音の世界を生み出していく。
狂言方が演じるもの
- アイ:前シテが中入りした際、ワキに改めて物語を進める役。狂言独特の明瞭な発声法で、観客にも能の筋がわかるように説明を行う。
演者芸歴
梅若万三郎
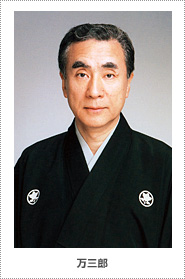 流名「観世流」シテ方
流名「観世流」シテ方
重要無形文化財総合指定保持者
初舞台:昭和19年(3歳)
初シテ:昭和23年 曲目「合甫」/昭和43年 「道成寺」初演
【海外公演】
昭和42年 第一回日本能楽団欧州公演 他
アメリカ・カナダ・メキシコ公演
昭和60年 ハワイ官約移民百年祭記念薪能公演
昭和61年 カナダ万国博覧会にて公演
平成元年 ベルギーユーロパリア日本祭参加
平成5年 ドイツ公演
【賞】
昭和63年 「松風」の演技にて大阪文化祭受賞
老女物以外の大曲、難曲を全て完演
平成4年 「野宮・合掌留」にて大阪文化祭賞受賞
平成9年 「卒都婆小町・一度之次第」にて大阪文化祭賞受賞
平成13年 11月23日 梅若万三郎 三世襲名
梅若万佐晴
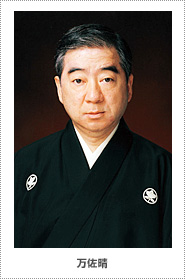 流名「観世流」シテ方
流名「観世流」シテ方
重要無形文化財総合指定保持者
初舞台 ...... 昭和24年 曲目「花筺」子方
初シテ ...... 昭和30年 曲目「合甫」/昭和33年 「道成寺」初演
【海外公演】
昭和42年より毎年ヨーロッパ各地で公演
昭和60年 ハワイ官約移民百年祭記念薪能公演
昭和61年 カナダ万国博覧会にて公演
平成元年 ベルギーユーロパリア日本祭参加
平成5年 ドイツ公演
過去の演目
| 日程 | 詳細 |
|---|---|
| 第1回 昭和55年 4月5日 | ◎善導大師1300年遠忌記念 能 杜若 土蜘蛛 狂言 悪太郎 |
| 第2回 昭和57年 5月29日 | ◎法然上人降誕850年慶讃記念 能 百万 笠之段 葵上 狂言 茶壷 |
| 第3回 昭和58年 5月7日 | 能 巻絹 橋弁慶 狂言 千鳥 仕舞 頼政 |
| 第4回 昭和59年 5月12日 | 能 羽衣 安達原 狂言 棒縛 仕舞 遊行柳 |
| 第5回 昭和60年 5月11日 | 能 半蔀 船弁慶 狂言 呼声 仕舞 山婆 昭和60年10月4~5日 ◎ハワイ官約移民100年記念 能 羽衣 葵上 船弁慶 土蜘蛛 狂言 梟 棒縛 |
| 第6回 昭和61年 5月10日 | 能 清経 天鼓 狂言 蝸牛 仕舞 源氏供養 |
| 第7回 昭和62年 5月9日 | 能 賀茂 土蜘蛛 狂言 附子 仕舞 桜川 |
| 第8回 昭和63年 5月28日 | 能 田村 鉄輪 狂言 二人大名 |
| 第9回 平成 元年 5月27日 | 能 熊野 安達原 狂言 佐渡狐 |
| 第10回 平成2年 5月26日 | 能 高砂 山婆 狂言 梟 仕舞 野守 |
| 第11回 平成3年 5月25日 | 能 松風 石橋 狂言 鎌腹 |
| 第12回 平成4年 5月26日 | 能 藤戸 昭君 狂言 清水 |
| 第13回 平成5年 5月29日 | 能 杜若 熊坂 狂言 鶏聟 |
| 第14回 平成6年 5月28日 | 能 弱法師 一角仙人 狂言 棒縛 |
| 第15回 平成7年 5月27日 | 能 高砂 紅葉狩 狂言 呼声 蝋燭能 能 鉄輪 狂言 地蔵舞 |
| 第16回 平成8年 5月25日 | 能 経正 葵上 狂言 六地藏 |
| 第17回 平成9年 5月31日 | 能 橋弁慶 三輪 狂言 船渡聟 |
| 第18回 平成10年 5月30日 | 能 天鼓 楊貴妃 狂言 惣八 |
| 第19回 平成11年 5月29日 | 能 金 札 船弁慶 狂言 伊文字 |
| 第20回 平成13年 5月26日 | 能 隅田川 半能 融 狂言 二千石 |
| 第21回 平成14年 5月25日 | 能 小督 吉野天人 狂言 鎌腹 |
| 第22回 平成15年 5月31日 | 能 千手 恋重荷 狂言 蝸牛 |
| 第23回 平成16年 5月29日 | 能 天鼓 望月 狂言 樋の酒 |
| 第24回 平成17年 5月28日 | 能 羽衣 船弁慶 狂言 棒縛 |
| 第25回 平成18年 5月27日 | 能 藤戸 狂言 昆布売 能 土蜘蛛 |
| 第26回 平成19年 5月26日 | 能 楊貴妃 狂言 附子 能 石橋 |
| 第27回 平成21年 5月30日 | 能 百萬 狂言 土筆 能 紅葉狩 |
| 第28回 平成22年 5月29日 | 能 鶴亀 狂言 鬼瓦 能 敦盛 |
| 第29回 平成24年 9月29日 | 能 鷺 狂言 蚊相撲 能 西行櫻 |
| 第30回 平成25年 9月28日 | 能 清経 狂言 栗焼 能 土蜘蛛 入違之伝 |
| 第31回 平成26年 9月27日 | 能 嵐山 狂言 伊文字 半能 半蔀 |
| 第32回 平成27年10月1日 | 能 杜若 狂言 昆布売 能 小鍛冶 白頭 |
| 第33回 平成28年10月1日 | 能 鶴亀 狂言 萩大名 能 紅葉狩―鬼揃 |
| 第34回 平成29年9月30日 | 能 雲林院 狂言 文蔵 能 安達原―白頭 |